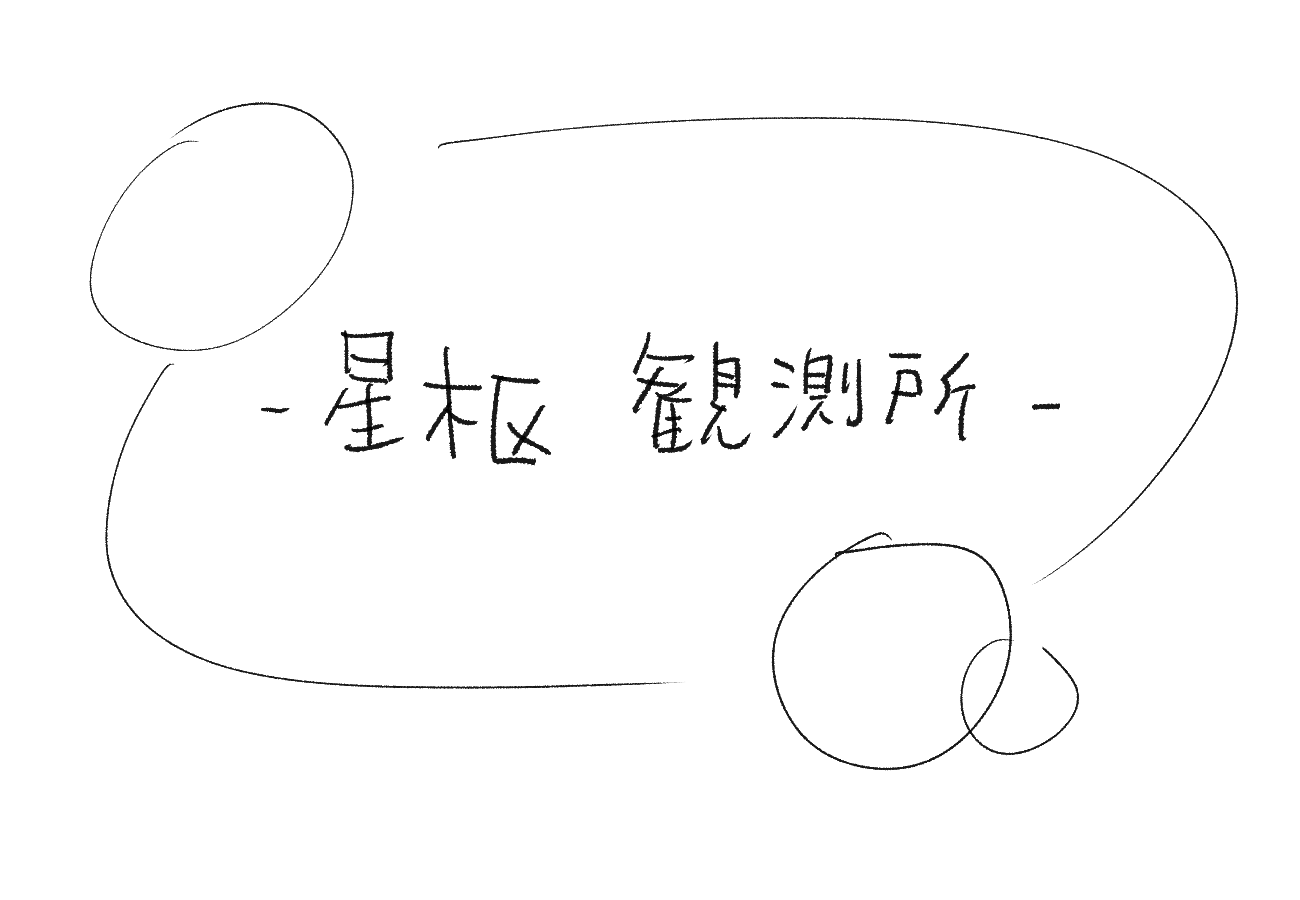「プールよりも前ずっと前のアリスちゃんと体育の授業」
まだ寒い、凍えるような一月の事。アリスのクラスでは体育の授業を行っていた。
けれど、アリスは毎回見学している。
「うー……」
そしてアリスは呻いている。健康そのもので、遊びまわるのが好きなアリスは、何故か毎回体育の見学を強制されている。保護者であるユリウスとノルベールにだ。
「過保護すぎるんだよぉっ!!」
そう、校庭にある、朝礼などで使われる高台の上に座っているアリスは叫んだ。
確かに過保護である。怪我したらどうとか、何かあったらこうとか、アリス達姉弟の保護者二人は、何かと過保護である。けれどアリスの弟であるアルトについては、男の子だからだろうか、普通に体育の授業も参加している。
まだ休み時間で、自由に動き回れるアルトはアリスに駆け寄って、手をぐぐっとのばして(アリスの背中にしか届かなかった)その背中に手を置いた。するとアリスは呻いて、アルトの腕にしがみついた。
「ボグもじゅぎょうであぞびだいいいいっっっ!!」
「姉貴、授業は遊びじゃないぞ。子供の遊びみたいなことやってるが、本人たちは至って真面目だ」
「あぞびじゃん――――今あぞびっでいっだじゃん――――――――」
着替え終わったらしい恵理が駆け付けて、アルトの真似をして手を大きく開き、ぴょんぴょんと飛び跳ね始めた。
「二人とも今日も楽しそうだね!」
「「楽しくないっっっ!!!」」
二人がそう仲良く返事をしたところで、授業開始のチャイムが鳴った。
二人はアリスの名残惜しい視線を背に、背の順で並んでいった。
そういえば、と恵理は考え始めた。
アリスとアルトは、ここ月宮町で、夜間幽霊などから町の人間たちを守るバイトを請け負っていた。それは、二人の保護者も知っている筈。ならば、何故、学校の授業だけは駄目なのだろうか――
アリスに視線をやると(目の前なのだが)、黒い長袖のセーラー服のアリスが高台の上に座って、幸せそうに手を振った。きっと恵理に振ったので、恵理は体操しながら小さくぱたぱたと手を振った。すると、アリスはすごく幸せそうに、全力で手を振り始めた。恵理は体操をしていてバランスを崩したので、手を振り返せなかった。
(2019年01月30日)
「アリスちゃんって日本語上手だよね」
ある十分休み、恵理は次の授業である国語のセットを、机の中からごっそり出して準備完了とした後、隣の席で携帯をいじくっているアリスに、ふと疑問が沸いた。「ねぇ、アリスちゃんって日本語上手いよね。覚えるのに何かコツとかあるの?」
恵理は英語が苦手だ。中学入って、最初に当たった英語の先生が、凄く性格のキツい先生だったのだ。故に、出だしは最悪で、そもそも暗記が苦手な恵理には最悪の相性だった。
アリスは、恵理の言葉に携帯を閉じて(この頃はまだガラパゴス携帯だった)、居心地悪そうに言葉を濁し始めた。けれど、暫くして、観念したようにため息をついた。
「ボク、ここに来る前アメリカに居たんだけど、学校とか通ってなくて、家庭教師だったの」
「へー、すごいじゃん!」
「すごいか分からない……いや、すごかった。その家庭教師が、すごかった」
「おぉ、つよかったんだね」
「強かった。えっと……スパルタ、だった。記憶を失ってから半年しか経ってないのに、あぁ、あああ、うわあああああ、」
「アリスちゃん!? 大丈夫!? 汗ひどいよ!? あと記憶喪失だったんだ!? そっちも大丈夫!?」
「ああああ……う、記憶は、戻ってないん、だけど、なんとかなってる……ぶい」
「全然びくとりーって無いよ!?」
ふにゅん、とアリスが落ち込んだ顔をしたので、恵理はその頭に手をのせてよしよし、と(実際はわしゃわしゃだったが)撫でると、アリスは下を向いたまま震えていた。手を離すと、そのまま机に突っ伏したので、恵理はまた変なこと聞いちゃったんだろうな、と反省した。
そして、今日の部活ではめいっぱい構ってやろうと、そう思った。
(2019年01月30日)
「生物の本質が見えるリタちゃんと」
「……海が見える」恵理と一緒に廊下を歩いていたアリスは、すれ違った女生徒を振り返り、小さくそんなことを言った。
今すれ違った少女は、恵理にも見覚えがある。少し前、部活の最中に突撃してきた依頼者の一人だ。
恵理達が所属するオカルト研究部の部長は、昔、校内で様々なオカルト的な悩み事を解決する、まぁだいたい何でも屋なんだのだが、つい最近まで休止していて、けれどもそれでもと依頼をしにくる生徒が時々いたらしく、よく幽霊部長ともなっている部活に隠れに来たのだ。確か、その時を切っ掛けに、何でも屋を再開したらしい。オカルト研究部を窓口にして。何故だ。
確か、その時の、女の子。
恵理の隣にいたアリスは、それを暫く見つめていたけど、すぐに興味を失ったように前を向いて歩きだした。
恵理はオカルト的なものに好奇心が旺盛なので、隣を歩くアリスに話しかけた。
「海って、どんなの?」
アリスは振り向きもせずに答えた。
「空気の感じ。温度が同じで息ができる水。そして、目で見る潮のにおい」
ゆら、と何かが思い浮かんだ気がした。
彼女の言葉は半分以上理解できなかったので、暫くその言葉について考えていた。
「……貴女は透き通りすぎている」
考え事をしている恵理は、彼女の言葉に気が付かなかった。
返事のない恵理にも、アリスはさした反応はなかった。
暫くして、恵理は答えが出たらしく、うんうんと頷いた。
「きっと、その世界は、すーっごく綺麗なんだろうなぁ」
アリスは目を伏せて、立ち止まった。
恵理を視界に入れないように逸らして、廊下端にあった消火栓を見ていた。
そして、遠ざかって、小さくなっていく恵理の背中を、やっとの思いで見た。
眩しそうに。
霞んで、消えてしまうようなものを見るように。
(2019年01月30日)